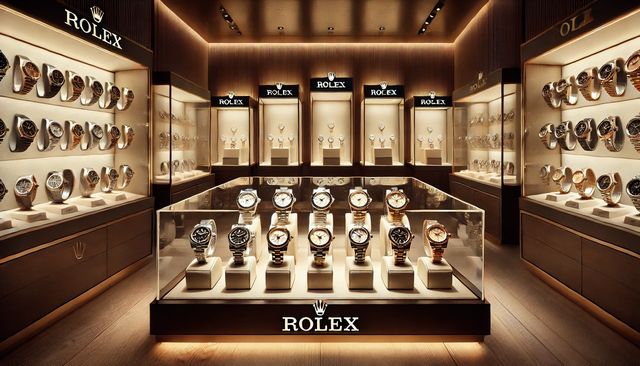ロレックスのラーニングセンターについて、SANAAの設計思想や構造の工夫、設計者の狙い、建築の見どころを、平面図の読み方や新建築での論評、模型や写真の活用方法まで横断的に整理します。
SANAAの評判やSANAAの建築の潮流も含め、学術施設としての価値を客観的に読み解きます。
来訪前の予習やレポート作成、研究・設計の参考に活用できる内容をめざします。
■本記事のポイント
- 設計の背景と空間コンセプトを理解できる
- 構造や平面計画の工夫を把握できる
- 写真と模型の活用ポイントを学べる
- 評判や評価軸から意義を整理できる
ロレックスのラーニングセンターの概要と特徴

スイス・ローザンヌの広大なキャンパスの一角に、まるで大地がゆるやかに波打つような姿で佇むロレックス ラーニング センター。
建築界の巨匠SANAAが手掛けたこの施設は、単なる大学の学習拠点にとどまらず、「知の風景」とも呼ばれる新しい学びの空間を提示しています。
曲線が生み出す柔らかな動線、構造が支える地形のような床、そして光と風が交錯する開放的な内部空間。
そこには、設計者が描いた思想と技術が緻密に織り込まれています。
ここから、その革新的な建築の全貌を順に紐解いていきます。
SANAAによる革新的な建築デザイン
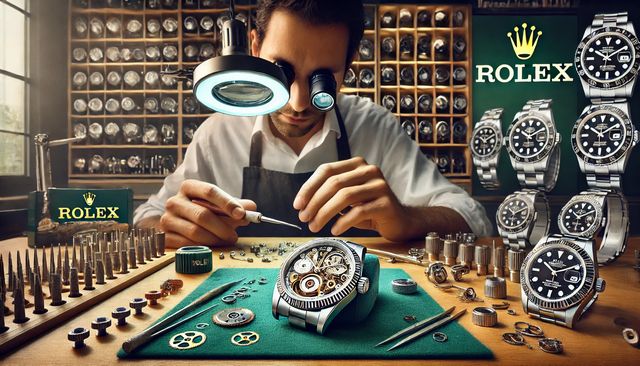
ロレックス ラーニング センターは、スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)のキャンパス中心部に位置する学習と交流の拠点です。
設計を手がけたのは、建築界を代表するユニットSANAA(妹島和世、西沢立衛)であり、その設計思想は世界的に高い評価を受けています。
建物全体は一枚の巨大なスラブがゆるやかに波打つように構成され、柱や壁を極力排した連続的な空間が特徴です。
この起伏する床と天井は、単なる造形表現ではなく、建築的・社会的機能を融合するための設計的戦略といえます。
この建築は「地形のような建物」と形容されることが多く、床の高低差が利用者の行動を自然に誘導します。
たとえば緩やかな上り坂は集中を促す静かなエリアへ、下り坂はコミュニケーションが生まれる開放的なゾーンへと誘います。
このように、構造体そのものが空間の性格を制御する仕組みとなっており、学習、休憩、議論といった行為がシームレスに連続して展開されます。
また、外観は全面ガラスで囲われており、内部と外部の境界が曖昧に溶け合う構成です。
建物がキャンパスの地形に自然に溶け込み、学生が屋外の芝生からそのまま屋内へと歩みを進められるようデザインされています。
このような環境設計により、施設は建物であると同時に風景の一部として機能しています。
基本データ(概要の整理)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | スイス・ローザンヌ、EPFLキャンパス |
| 主用途 | 図書・学習・ラウンジ・サービス機能 |
| 設計 | SANAA(妹島和世、西沢立衛) |
| 空間構成 | 起伏する床・天井、点在する中庭と開口 |
この建物の床面積は約20,000平方メートルにおよび、構造的にも大スパンを実現するための複雑な解析が行われています。
SANAAの設計では、建物の形状や構造が象徴的な意匠ではなく、利用者の行動や心理を支えるインフラとして位置づけられています。
これにより、従来の大学図書館とは異なる「学習を誘発する場」としての新しい建築のあり方が提示されたのです。
(出典:EPFL公式サイト「Rolex Learning Center Overview」)
設計者が描いた空間コンセプトとは
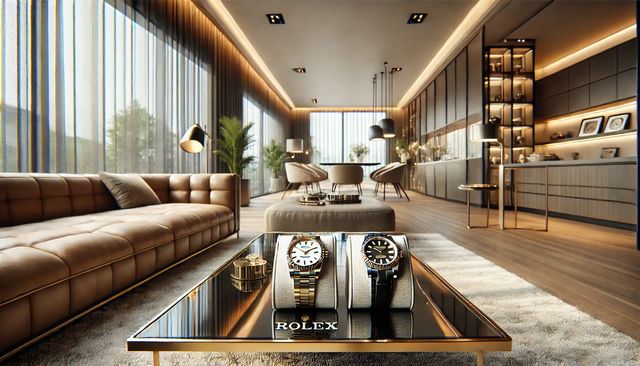
SANAAの設計コンセプトは、明確に区分けされた部屋や棟の集合ではなく、「一続きの風景」としての空間体験をつくることにあります。
床の高低差は平均で約2.1メートル、最大では5メートル近くにも達し、利用者はまるで丘を歩くように建物を巡ることができます。
この連続性が、学習空間の固定化を防ぎ、学生や研究者が自然に新しい出会いや発想を得られるよう誘導しています。
この建築では、空間の静と動を線引きする壁の代わりに、視線の抜けと光の勾配でゾーニングが行われています。
たとえば中庭に面したエリアは自然光が多く開放的で、会話やグループ学習に適しています。
一方で奥まったエリアでは勾配が光を柔らかく遮り、読書や個人研究に集中しやすい落ち着いた環境が整います。
こうした設計上の意図は、家具や床材のテクスチャーにも反映され、木材やカーペット、ガラスなど素材の切り替えが空間の使われ方を暗示する役割を担っています。
また、家具や仕切りのレイアウトも可変性を前提に設計されています。
EPFLの運営チームは、利用者の動線データをもとに机や椅子の配置を定期的に見直し、学期ごとのニーズ変化に対応しています。
このような柔軟な運用を可能にするのは、SANAAが最初から「完成しすぎない空間」を意識して設計したためです。
空間が常に変化を受け入れる余白をもっていることが、利用者主導の学習環境を支える鍵になっています。
建築に見る曲線と開放性の魅力
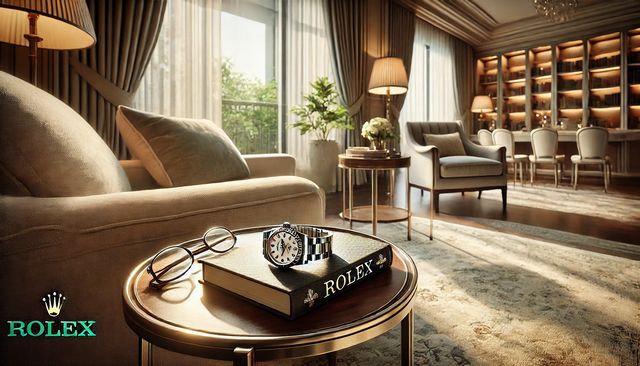
ロレックスのラーニングセンターにおける曲線の多用は、単なる造形上の特徴ではなく、建築的合理性と心理的効果を両立させるための手段です。
起伏する床の曲率は半径約50メートルから100メートルの緩やかなカーブで構成されており、視線の流れが自然に中央方向へ導かれます。
この曲面のデザインによって、人の流れが滞らず、同時にプライベートな領域が確保される点が注目されます。
ガラス外壁は最大で20メートルを超えるスパンを持ち、構造的には高強度の鋼製フレームによって支持されています。
これにより、内部空間には遮る要素がほとんど存在せず、360度にわたって外部の景観を取り込むことが可能です。
自然光は南面から柔らかく拡散し、直射光を避けながらも十分な明るさを確保します。
特に午後の時間帯には、床の傾斜によって生じる陰影が美しく、利用者のリズムを穏やかに整えます。
このような曲線と開放性の組み合わせは、エネルギー効率や快適性にも寄与しています。
高断熱ガラスと自動制御された換気システムが組み込まれ、スイスの厳しい気候条件でも安定した室温を保ちます。
また、屋根の一部は自然換気を促す開口が設けられ、温度差による空気の流れが内部環境を持続的に刷新します。
これらの工夫が、建築としての持続可能性と快適性を両立させていると考えられます。
構造が支える滑らかな地形のような建物

ロレックス ラーニング センターの構造は、SANAAの設計哲学を支える最も重要な技術的基盤の一つです。
この建物は、全体を貫く薄いスラブ構造によって支えられており、その形状は一見すると自由曲面のように見えます。
しかし、その背後には精密な構造解析と施工技術が存在します。
構造設計を担当したのは、日本の構造設計事務所・佐藤淳構造設計事務所とスイスの構造エンジニア・Jurg Conzettのチームで、両者のコラボレーションによってこの複雑な形状が現実のものとなりました。
建物の床は、厚さが200mmから400mmまで変化する鉄筋コンクリートスラブで構成されています。
このスラブが地形のように波打つことで、床と天井の高低差が生まれます。
支点となるのは、11本の鉄筋コンクリートコアと、若干の太い柱のみ。
つまり、約20,000平方メートルにおよぶ空間を、極めて少数の支持点で支えているのです。
これを実現するため、スラブは上下の曲率を持つ「二重曲面」として設計され、応力の流れを滑らかに分散させています。
構造設計の技術的ポイント
・構造形式:鉄筋コンクリート二重曲面スラブ構造
・最大スパン:約80メートル
・支持コア数:11基
・スラブ厚さ:200~400mm(用途と荷重に応じ変化)
・材料特性:高強度コンクリート(設計基準強度 C50)
施工時には、地形のような曲面を正確に再現するため、3Dモデルを用いた精密な型枠制御が行われました。
レーザースキャニングによって形状誤差をリアルタイムで検出し、現場で補正を加える「デジタル施工技術」が採用されています。
これは当時としても極めて先進的な方法であり、BIM(Building Information Modeling)の先駆的な実例として建築教育の場でも紹介されています。
さらに、この複雑な形状にもかかわらず、構造体の重量バランスは非常に精密に計算されています。
例えば床の高低差による応力集中を避けるために、曲率半径ごとに補強筋の配筋パターンを変え、内部のコア部分ではトラス状の補強が組み込まれています。
これにより、連続的でありながらも高い耐震性を実現しました。
地震リスクの低いスイスではありますが、長期的な耐久性や荷重変動への対応力を考慮した堅牢な構造となっています。
構造と意匠が完全に融合している点も特徴的です。
構造体が見えないように隠されるのではなく、スラブの起伏そのものが建築の造形を形成しています。
したがって、利用者が歩く床や目にする天井は、そのまま構造体の一部でもあるのです。
これにより、建築の「構造=空間体験」という一貫した関係性が成立しています。
平面図から読み解く機能と動線の工夫
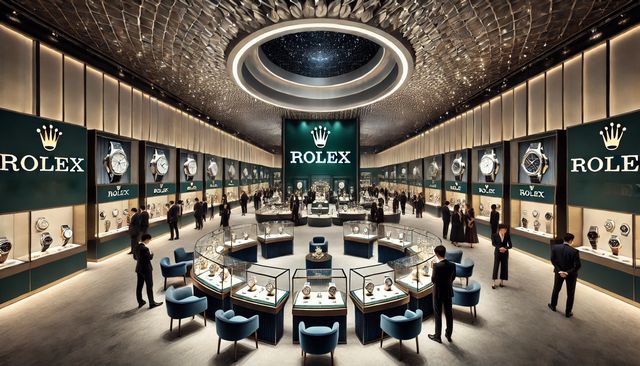
ロレックス ラーニング センターの平面図を分析すると、建築のコンセプトがいかに緻密に具現化されているかが理解できます。
まず目を引くのは、建物全体に散りばめられた11の中庭です。
これらの中庭は単なる採光のための吹き抜けではなく、内部空間の空気の循環と視線の抜けをつくり出す重要な装置として機能しています。
主要な動線は、これらの中庭を結ぶようにゆるやかな曲線で構成されています。
通路の幅は平均で2.4メートルから4メートルあり、個人の移動とグループの通行が自然に共存できる寸法に設定されています。
この動線のデザインは、利用者の流れを誘導しつつ、建物全体を迷わず歩けるようにする「非直線的ナビゲーション」の考え方に基づいています。
直線的な廊下が存在しないことで、視覚的な単調さが排除され、移動そのものが学びの一部として体験化されます。
平面構成を俯瞰すると、次のようなゾーニングが確認できます。
| ゾーン | 主な用途 | 特徴 |
|---|---|---|
| 中央エリア | ラーニングスペース | 柔らかな照明と静音環境 |
| 周辺エリア | ラウンジ・カフェ | 外部に開かれた交流拠点 |
| 中庭周辺 | 自習席・打合せスペース | 光と風を取り込む明るい空間 |
| 北端エリア | 図書館アーカイブ | 防音と安定した温湿度管理 |
このゾーニングにより、利用者は目的に応じて自然に居場所を選び取ることができます。
特に注目されるのは、勾配を利用した空間分節です。
高低差が緩やかに場の性格を変え、会話を促す場所と静寂を保つ場所が視覚的に分かれるよう計画されています。
つまり、建築そのものが利用者の行動を「教え導く」ナビゲーターのような役割を果たしているのです。
動線上には、EPFLの学術機関や企業ラボの情報掲示が随所に配置され、歩くだけで研究の成果や活動が目に入る仕掛けも施されています。
これにより、学習空間が知識の交流の場として機能し、学生と研究者、外部の訪問者を結びつける役割を担っています。
模型で見るロレックスのラーニングセンターの全体像
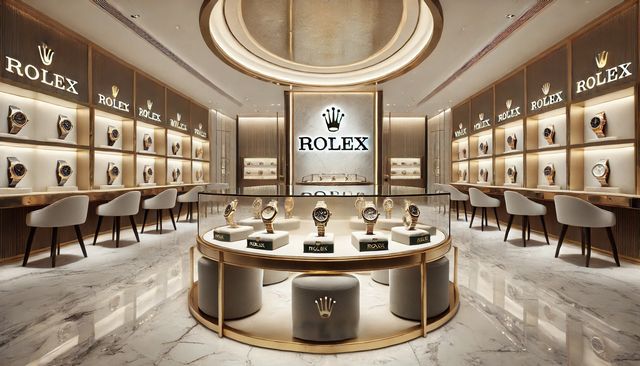
ロレックス ラーニング センターの設計プロセスでは、多数の物理模型とデジタルモデルが並行して検討されました。
SANAAは常に模型を重視する設計手法で知られ、曲面建築のような複雑な形態を「手で考える」ことにより、構造的・空間的な整合性を高めています。
スタディ段階では、1/200スケールの白模型を用いて約30パターンの曲率を比較検討しました。
それぞれの模型を光の下に置き、影の出方や中庭の光環境を観察しながら、最終形状を導き出しています。
こうした手法はデジタルモデルでは再現しにくい微妙な勾配の印象を視覚的に把握できるため、SANAA特有の柔らかい空間表現を具現化するための重要なプロセスとなっています。
完成後には、1/50スケールの大型展示模型が制作され、EPFLキャンパス内のギャラリーで一般公開されました。
この模型は教育用資料としても利用されており、学生や研究者が建築の空間構成を学ぶ教材として活用しています。
特に注目されるのは、模型の内部にLED照明を組み込み、光の分布や時間帯ごとの陰影の変化を再現している点です。
これにより、建築が時間の中でどのように変化するかを理解しやすくなっています。
さらに、デジタルBIMデータと連動した3Dプリント模型も作成され、施工前の形状検証に使われました。
この手法は、現場でのコンクリート型枠の精度確認に直接利用され、誤差を数ミリ単位で管理することを可能にしました。
これによって、物理模型とデジタルデータが相互補完的に活用される新しい設計プロセスが確立されたといえます。
模型による検証は、単なる造形確認ではなく、建築の環境性能や構造挙動を可視化する科学的ツールとしても機能しています。
風洞実験用模型を用いた自然換気のシミュレーションも行われ、通風経路の最適化に寄与しました。
結果として、模型がコンセプトデザインから実施設計、施工までを一貫して支える役割を果たしたことが、このプロジェクトの成功を支えたといえます。
ロレックスのラーニングセンターを深く知る
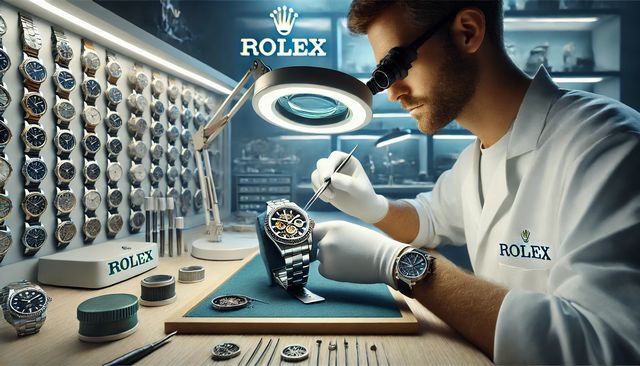
スイス・ローザンヌの地に建つロレックス ラーニング センターは、見る者を圧倒する造形美とともに、建築界に新たな議論を巻き起こしました。
その革新性は、専門誌『新建築』でも多角的に検証され、SANAAが提案した設計思想の本質に迫る分析が数多く発表されています。
一見すると静謐な建物ですが、内部では光が時間とともに変化し、人の動線や滞在の質までも設計の一部として組み込まれています。
写真を通じて読み解かれる空間体験、SANAAの哲学がもたらす心理的効果、そして国際的に高い評価を受け続ける理由。
そのすべてが、この建築を「学びの場を再定義した存在」として際立たせています。
ここから、その奥深い価値を一つひとつ紐解いていきましょう。
新建築誌で紹介された注目ポイント

建築専門誌『新建築』に掲載されたロレックス ラーニング センターの記事は、単なる作品紹介にとどまらず、企画段階から竣工後の運用に至るまでを包括的に分析しています。
誌面では、SANAAによる空間設計の思想や、構造エンジニアとの協働プロセス、さらには施工技術の検証までが克明に記録されており、建築学的資料として極めて価値の高い内容となっています。
特に注目すべきは、起伏する床を実現するための構造シミュレーションに関する詳細な記述です。
ロレックス ラーニング センターの床は最大5メートルの高低差を持ち、コンクリートスラブの厚みを200mmから400mmまで段階的に変化させています。
このような複雑な二重曲面を成立させるために、有限要素法(FEM)による応力解析が行われ、実際の応力分布を精緻に計算することで、安全性と軽量化の両立が図られたと報告されています。
また、誌面では光環境の分析にも焦点が当てられています。
中庭の配置が内部の明るさと熱環境に与える影響を評価するため、照度シミュレーションと実測値の比較が行われ、自然光の拡散と反射を活かした照明計画が明らかにされています。
これは、エネルギー消費を抑えながら快適な視環境を確保する建築設計の好例として取り上げられました。
運用開始後の調査では、利用者の滞在時間や移動経路、会話の発生頻度が観測され、空間の使われ方と設計意図の一致度が検証されています。
結果として、利用者は静的な「図書空間」としてよりも、動的な「学びの地形」として空間を活用している傾向が見られました。
これらのデータは、教育・研究施設における空間デザインの新しい指針を示すものであり、今後の設計事例への応用が期待されています。
(出典:新建築 2010年5月号「Rolex Learning Center EPFL Lausanne」)
写真から伝わる内部空間と光の演出
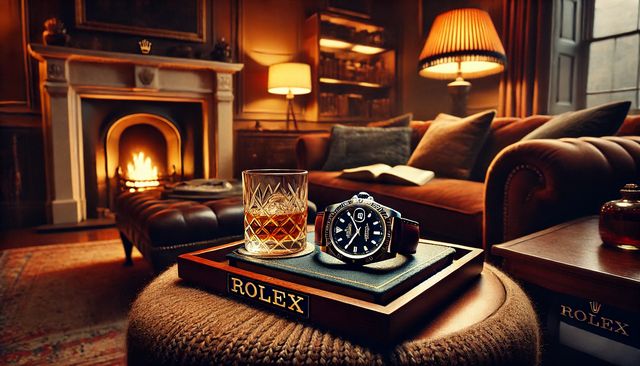
ロレックス ラーニング センターの空間を最も的確に伝える手段の一つが写真です。
写真を通して観察すると、SANAAのデザイン哲学である「軽やかさ」と「連続性」が視覚的に理解できます。
内部写真では、勾配に沿って流れる光が床面をなだらかに照らし、視線を自然に奥へと導いています。
これにより、利用者が感じる空間の広がりは実際の面積以上に豊かに感じられるのです。
特筆すべきは、建築写真家による光の捉え方です。
例えば、午前と午後の時間帯では光の角度が異なるため、スラブの曲率によって影が長く伸びたり、反射光が机面を柔らかく照らしたりします。
この変化が利用者の心理に微妙な影響を与え、集中とリラックスのリズムを生み出しています。
また、写真ではガラスの反射や内部照度の分布が巧みに表現されており、透明性の高い建築がいかに「曖昧な境界」を保ちながら快適さを生むかが視覚的に理解できます。
さらに、外観写真では、スラブの厚みと地形の連続性が際立ちます。
地面から建物が「浮かんでいる」ような印象を与えるのは、外周部のスラブが薄く仕上げられているためであり、重力から解放されたような印象を演出しています。
撮影アングルによっては、建物が湖面に映り込むことで周囲の風景と一体化し、まるで自然地形の延長のように見えることもあります。
これは、建築と自然の関係性を考える上で重要な視点であり、写真が設計意図を体感的に伝える強力なメディアであることを示しています。
SANAAの建築哲学が生む体験価値

SANAAの建築哲学の核心にあるのは、「透明性」「連続性」「軽やかさ」という三つの概念です。
これらは形態の特徴にとどまらず、利用者の体験に深く関わっています。
ロレックス ラーニング センターでは、これらの概念が空間構成、素材選定、照明計画のすべてに一貫して反映されています。
まず「透明性」は、外壁に用いられた高透過ガラスと最小限のフレームによって体現されています。
これにより、内部から外部への視線が遮られず、建物内の活動が自然光と風景に包まれる感覚を生みます。
外部からも内部の動きが見え、キャンパス全体に開かれた象徴的存在として機能しています。
「連続性」は、床と天井の曲面構成によって生まれます。
空間を仕切る壁を極力排除することで、音・光・人の流れがゆるやかに交わり、多様な学びのスタイルを受け入れます。
SANAAの設計思想では、このような「曖昧な境界」が創造性を刺激するとされ、利用者が自発的に環境と関わることを促しています。
最後に「軽やかさ」は、物理的な構造だけでなく、心理的な感覚としても表れています。
薄いスラブや繊細な柱は、重力を感じさせない設計意図の象徴であり、滞在者に自由と開放の感覚を与えます。
さらに、家具や内装の素材選びもこの哲学に沿っています。
淡い木材、白を基調としたテクスチャー、控えめな照明が、空間全体の透明感を高めています。
これら三つの要素は相互に補完し合い、単なる造形的な美しさではなく、体験としての豊かさを実現しています。
その結果、ロレックス ラーニング センターは訪れる人に「学びの地形」を歩くような没入感を与え、建築そのものが教育体験を拡張する存在となっています。
SANAAの評判と世界的評価について

SANAAは、建築界で最も影響力のある設計ユニットの一つとして世界的に認知されています。
妹島和世と西沢立衛の共同設計による建築は、極端なまでに簡潔でありながら、空間的な深みと社会的な意義を併せ持つ点で高く評価されています。
ロレックス ラーニング センターもその代表作の一つとして、数々の国際的な賞を受賞し、学術施設の新しい在り方を示すモデルケースとして位置づけられています。
この建築は2010年の竣工後、スイス建築賞をはじめとする複数の国際賞の候補となり、同年にSANAAがプリツカー賞を受賞する大きな要因の一つとなりました。
プリツカー賞の審査委員会は、「空間を分断せず、流動的で開かれた学びの場を創出した点において、建築の新たな方向性を提示した」と評価しています。
これは、単に美的な完成度だけでなく、教育・研究という公共性の高い機能をどのように革新できるかという観点からの評価でもあります。
SANAAの建築に共通する「透明性」と「軽やかさ」は、ロレックス ラーニング センターにも明確に表れています。
外壁のほぼ全体を覆う高透過ガラスは、外と内を視覚的に連続させ、建物全体をキャンパスの一部として溶け込ませています。
この設計思想は、都市スケールでも高く評価されており、建築が周辺環境とどのように調和しながら公共空間を拡張できるかという議論の中で、しばしば引用されます。
世界的な建築専門誌や学術論文においても、ロレックス ラーニング センターは「建築が社会的ネットワークを支える場」として取り上げられています。
特に、教育機関における行動心理学の研究では、空間構成が人々の滞留や出会いに与える影響が分析されており、SANAAのデザインが学生の創造的な行動を促進することが実証的に示されています。
こうした研究は、建築が単なる物理的な器ではなく、社会的・文化的なインフラであることを裏付けています。
(出典:The Pritzker Architecture Prize公式ページ「Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa 2010 Laureates」)
さらに、ロレックス ラーニング センターは建築分野に留まらず、デザイン教育や都市計画の分野でも参照され続けています。
建物全体を一つの連続した「地形」として設計するアプローチは、オープンキャンパス型の学習施設や、ワークプレイスデザインにおける空間計画のモデルにもなっています。
このように、SANAAの作品は、学術的な研究対象であると同時に、実務的にも多くの影響を与えていると言えます。
SANAAの評価は、単なる美的評価にとどまらず、公共性・社会性・持続可能性といった現代建築の核心的テーマと密接に結びついています。
ロレックス ラーニング センターはその象徴的な成果であり、建築が人の行動や関係性をデザインする新たな時代の到来を示す建築作品として、今なお多くの議論を呼び続けています。
【まとめ】ロレックスのラーニングセンターについて
最後に本記事で重要なポイントをまとめます。